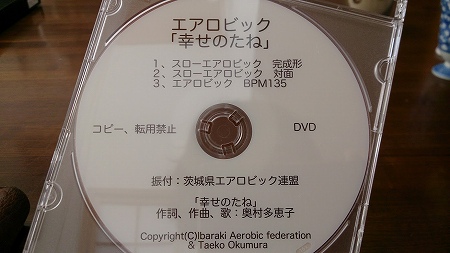毎日新聞 20151202
国際平和ポスター・コンテスト
県内から2作品 常総の松崎さん、取手の野川さん
「国際平和ポスター・コンテスト」(ライオンズクラブ国際協会主催)への出品作を決める国内最終審査に、県内からは常総市立石下小6年、松崎綾乃さん(11)と取手市立白山小6年、野川佳鈴さん(11)の2作品が臨むことになった。通常は1作品だが「どちらも優れている」として異例の2作品に。今月中旬の国内最終審査を通過すれば、年明けの世界審査(米国)に進む。【安味伸一】
平和の大切さを考えようと、11〜13歳の児童・生徒を対象に募集し、毎回、世界各国から約35万点の応募があるという国際コンテストだ。今回のテーマは「平和を分かち合おう」。県内の応募総数は約2700点。県内を範囲とする「同協会333−E地区」が審査し、県代表を決めた。
知事賞に輝いたのは松崎さんの作品。鯨や魚が泳ぐ地球の両側にハトの翼が広がり、その上で子供たちが手をつなぐ。松崎さんは「世界中の人たちが平和で仲良く暮らしていけるようにと思って描いた」と話す。
野川さんには協会の地区ガバナー(代表)賞が贈られた。広島市の原爆ドームや「原爆の子の像」の上に万国旗がはためく。像になった少女が「平和になって生き返るように」(野川さん)との願いを込めた。
11月21日には県庁で同地区の表彰式があり、山口やちゑ副知事と下川利澄ガバナーから賞状が贈られた。入賞は両賞を含め計23点。式で山口副知事は「どれも個性がある。絵の中に地球の平和を込めて描かれたことは素晴らしい」と称賛した。
県代表2点は新潟、栃木、千葉、群馬、茨城5県の複合地区審査を受ける。同地区を含めた国内7作品は世界選考に進み、選ばれた24作品はインターネットや移動博覧会などを通じて世界各地で紹介される。