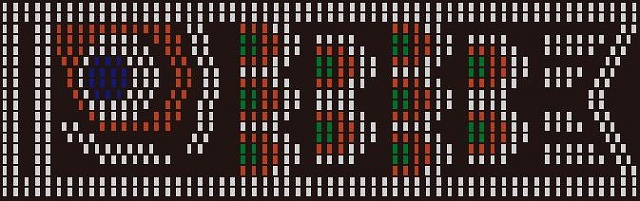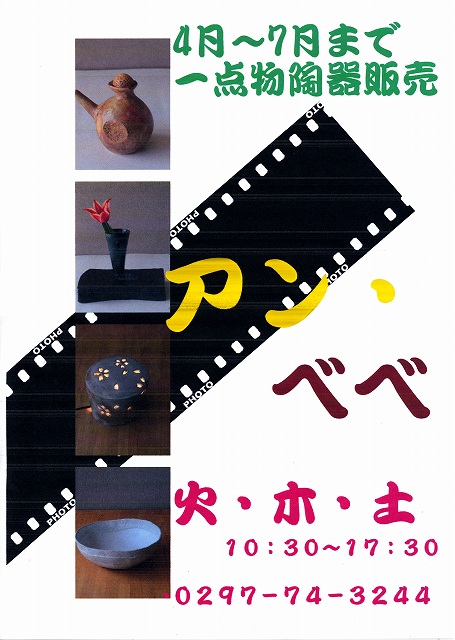2013.4.22 03:07 [産経抄]
ホタテの刺し身は、今や日本人にとってもっともなじみ深い料理のひとつだろう。かつては、干し貝柱にするのが一般的だった。昭和30年代前半まで主流だった、稚貝を放流する「増殖」では、貝のなかに砂が入る難点があったからだ。生産効率も悪かった。
▼ところが、ホタテ貝の端に穴を開けロープでつるす、「耳づり」という画期的な養殖法を考え出した人物がいる。岩手県大船渡市に住んでいた千葉繁さんだ。2年前の東日本大震災による津波に襲われ、自宅で妻のサダさんとともに亡くなった。88歳と81歳の夫婦だった。
▼もともと大船渡湾でカキの養殖に携わっていた千葉さんは、昭和35年のチリ沖大地震の津波でも大きな被害を受けている。その復興工事のために出稼ぎに来ていた漁業従事者を通じて、江戸時代からホタテの産地だった青森県の陸奥湾と縁ができた。
▼カキ養殖の方法を参考に、陸奥湾でサダさんとともに試行錯誤を重ね、ついに「耳づり」方式に行き着く。最初はどこの魚市場でも相手にされなかったという。砂の入っていないホタテなど、当時あり得なかった。
▼千葉さんは、ノウハウを惜しみなく指導した。改良が重ねられ、現在北東北、北海道のホタテ養殖は600億円を超える産業となっている。その経緯は、今年3月11日に出版された夫妻の伝記『ホタテの神さま』(盛岡出版コミュニティー)にくわしい。千葉さんと長年交流のあった前大船渡市長の甘竹勝郎さんらが資料を集め、作家の松田十刻さんがまとめたものだ。
▼津波で全滅した大船渡市のホタテ養殖は、復興を果たしつつある。甘竹さんはいう。「千葉さん夫婦の苦闘の歴史を広く知ってもらうことで、地元はもっとがんばれると思うのです」
産経新聞20130422 産経抄
ホタテの刺し身は、今や日本人にとってもっともなじみ深い料理のひとつだろう。かつては、干し貝柱にするのが一般的だった。昭和30年代前半まで主流だった、稚貝を放流する「増殖」では、貝のなかに砂が入る難点があったからだ。生産効率も悪かった。
ところが、ホタテ貝の端に穴を開けロープでつるす、「耳づり」という画期的な養殖法を考え出した人物がいる。岩手県大船渡市に住んでいた千葉繁さんだ。2年前の東日本大震災による津波に襲われ、自宅で妻のサダさんとともに亡くなった。88歳と81歳の夫婦だった。
もともと大船渡湾でカキの養殖に携わっていた千葉さんは、昭和35年のチリ沖大地震の津波でも大きな被害を受けている。その復興工事のために出稼ぎに来ていた漁業従事者を通じて、江戸時代からホタテの産地だった青森県の陸奥湾と縁ができた。
カキ養殖の方法を参考に、陸奥湾でサダさんとともに試行錯誤を重ね、ついに「耳づり」方式に行き着く。最初はどこの魚市場でも相手にされなかったという。砂の入っていないホタテなど、当時あり得なかった。
千葉さんは、ノウハウを惜しみなく指導した。改良が重ねられ、現在北東北、北海道のホタテ養殖は600億円を超える産業となっている。その経緯は、今年3月11日に出版された夫妻の伝記『ホタテの神さま』(盛岡出版コミュニティー)にくわしい。千葉さんと長年交流のあった前大船渡市長の甘竹勝郎さんらが資料を集め、作家の松田十刻さんがまとめたものだ。
津波で全滅した大船渡市のホタテ養殖は、復興を果たしつつある。甘竹さんはいう。「千葉さん夫婦の苦闘の歴史を広く知ってもらうことで、地元はもっとがんばれると思うのです」