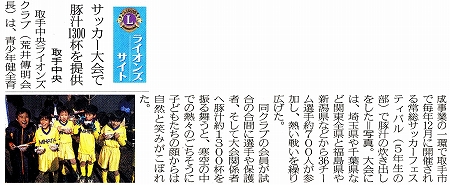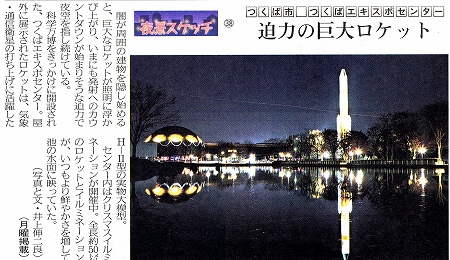茨城新聞20150114
Posts Tagged ‘茨城新聞’
取手市 止まらない人口減
金曜日, 1月 17th, 2014常総サッカーフェスティバル
火曜日, 1月 14th, 2014賀詞交歓会にサプライズ 美馬投手
木曜日, 1月 9th, 2014茨城新聞 デスク日誌
金曜日, 1月 3rd, 2014茨城新聞 20140103
動画ニュース 初日の出、名所一番太鼓響く
茨城新聞 デスク日誌
新しい種子生かす年に
午(うま)年となる新年が明けた。駆け抜ける駿馬のような飛躍の年にしたいと願う。
しかし、午は杵(きね)の原字で、上下に交差して餅をつく杵を描いたものだという。
前半が終わり、後半が始まる位置を指すので、昼の12時は「正午」という。
十二支の中間に当たり、植物の成長期が終わって、衰え始めた状態を表しているのが午らしい。
なんだか勢いをそがれる気もするが、未来に向かって、これまでを振り返る年にすればいいのだろう。
人口減少の始まった日本。
右肩上がりの成長が続く事はもうないだろう。
ならば、成熟期を迎えた日本の将来像をじっくり考える年にするべきなのかもしれない。
衰え始めた草木も新しい種子を残しているはず。
その種子をどうやって生かしていくか、少しだけ考えてみたい。(大子常陸大宮支局・津留伸也)
茨城新聞 いばらき春秋
「正月から大変ですね」。元日。立ち寄ったコンビニエンスストアでレジの店員に声を掛けた。
「いつもご利用ありがとうございます。今年もよろしくお願いいたします」。
丁寧な返事が返ってきた。
働く姿は美しい。
地道に一生懸命生きる人が報われる年になるといい。
新年を迎え、そう思った
食卓に家族がそろい雑煮を食べる。
初詣に出掛け、健康や家内安全を願う。
届いた年賀状を見ながら、友人や知人の近況に思いをめぐらす-。
日常の仕事から解放され、のんびりと正月休みを過ごしている人も多いだろう。
駅伝、サッカー、ラグビー…。スポーツのテレビ観戦も正月の楽しみの一つといえる。
特に県勢の活躍には応援にも力が入る。
きのうの全国高校サッカーは、水戸啓明高がPK戦を制し、3回戦へ駒を進めた。
全国大学ラグビーでは筑波大が早大に敗れ、惜しくも決勝進出はならなかった
今年はロシアのソチで冬季五輪、ブラジルではサッカーW杯が行われるなど大きなスポーツ大会が続く。
新ポスティングシステムを利用して米大リーグへの移籍を目指している田中将大投手の動向も注目だ。
アスリートの躍動に期待が高まる2014年でもある。(柴)
余録:駅伝は今や正月の風物詩である。元日には… 毎日新聞 20140103
駅伝は今や正月の風物詩である。元日には実業団の全国大会「ニューイヤー駅伝」で、五輪を目指す実力者や勢いのある若手が寒風の中を駆(か)け抜けた。
2、3日は大学生の箱根駅伝だ。テレビの前にくぎ付けの人も少なくないだろう
海外ではほとんど行われないこの競技が、国内でこれほどの人気を集めるのはなぜか。
「寒い冬に汗でにじんだタスキをつなぐ駅伝には観戦者の心をつかむエッセンスがたくさん詰まっている」。
高校、大学時代に駅伝でならした順天堂大陸上部女子監督の鯉川(こいかわ)なつえさんは、本紙への寄稿でそう解説している
確かに、一本のたすきがチームの絆(きずな)になり、一人一人から限界ぎりぎりの頑張りを引き出す。
たすきを手渡したとたん、力尽きて倒れ込む選手の姿はその象徴といえよう。
集団を尊ぶ意識や自己犠牲の精神が、日本人の心の深いところと共振するのかもしれない
レースで大差がつくと、前の走者が中継所に着く前に次の走者がスタートする場合もある。
たすきのリレーが途切れるということだ。渡せなかった無念はいかばかりか。
たすきは世代を超えて先輩から後輩へ、過去から現在へと託(たく)されたものだからこそ重いのだ
私たちは敗戦からの復興、そして高度成長を経た先輩たちから平和と豊かさを受け継いだ。
しかし今、それらが脅(おびや)かされているように思う。
安全保障や外交をめぐる政府・与党の論議は国民の安全を担保できるのか。
アベノミクスは社会的な弱者の暮らしを守れるのか
政権や政策を選ぶのは今を生きる国民である。先人から託されたたすきを次代にリレーする責任をかみしめたい。
つくばランタンアート2013
日曜日, 12月 15th, 2013茨城新聞20131215 夜の街にランタン6000個つくば
手作りランタン約6千個を使った「ランタンアート2013」が14日、つくば市吾妻のつくばセンター広場などで始まった。
日没を迎えると、優しい明かりが街を包み、訪れた人を楽しませた。
つくばセンター地区活性化協議会が主催し今年で5回目。
障子紙に絵を描いた「絵付きランタン」や色画用紙を切り抜いて模様を付けた「切り抜きランタン」などが並ぶ。
センター広場には、市立竹園東中学校の生徒らによる作品「芽吹けつくば」を展示
。約1200個のランタンで、2枚の若葉を付けた芽、星、滴などを表現した。
同中2年の石田傑君(14)は「きれいに並べることができた。多くの方に見てほしい」と話していた。
15日も午後4時45分から午後7時半まで点灯される。
茨城新聞動画ニュース
茨城新聞20131216 大好きな光景をご紹介!
取手特産品インターネットショップ『とりで本舗スタート』
木曜日, 12月 12th, 2013茨城新聞20121212
とりで本舗に入ってみると・・・
クリスマスのpresentにも使えそうなシュトーレンもありました。
今回のネット販売サイトは、県内初
新商品もございますので是非一度ご覧くださいね。
毎日新聞20131213
茨城新聞20131212
 神栖市の特産品を使った『ピーマンうどん』も大好評なんですよね。
神栖市の特産品を使った『ピーマンうどん』も大好評なんですよね。
とりでの特産品 『トマトライス』ってどうかなぁ?
「常陽新聞」復活へ 県南地域情報に特化
水曜日, 12月 4th, 2013茨城新聞20131202
タブロイドと電子版セット
8月に廃刊となった土浦市を中心とする日刊紙「常陽新聞」が、来年1月中旬から2月上旬の間に、タブロイド判(通常新聞の2分の1サイズ)で復活する見通しであることが1日、関係者の話で分かった。
社名は常陽新聞株式会社(本社・つくば市吾妻)で、資本金2千万円を都内のコンサルティング会社が100%出資。題字「常陽新聞」を引き継ぎ、12ページの宅配タブロイド判と電子版のセットで、日曜休刊の週6日発行を予定している。
人口増加の著しいつくばエクスプレス沿線や、土浦市を中心とするJR常磐線沿線の地域情報に特化し、20〜40代の子育て世代を重点に情報を提供していく方針で、フリーペーパーなどとの競合も予想される。電子版ではネットメディアの特性を生かした情報発信や広告ビジネスの展開を目指すという。
発行部数は3千部程度からのスタートを見込み、購読料は月額2千〜2200円程度、1部売り100円程度を予定している。
社員数は約15人で、旧常陽新聞社の社員が主力となる模様。つくば、土浦両市をメーンに県南地域で最大13市町村での展開を目指しているといい、北は石岡、南は守谷、取手、龍ケ崎、稲敷の各市が対象地域という。
12月半ばにプレ版を発行して対象エリア内に無料で配り、既存読者の掘り起こしと新規読者の開拓を図る。
IT企業出身の楜沢悟社長は「詳細は本格創刊の際に発表しようと考えている」としている。
取手聖徳女子中高校が共著
火曜日, 12月 3rd, 2013つくば『光の森』点灯式
水曜日, 11月 27th, 2013茨城新聞動画ニュース~