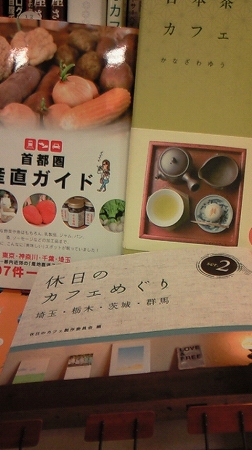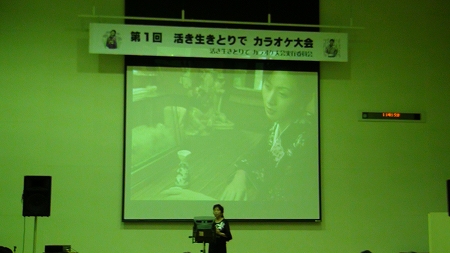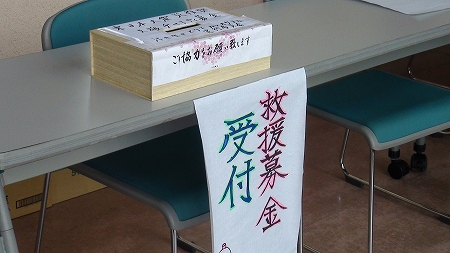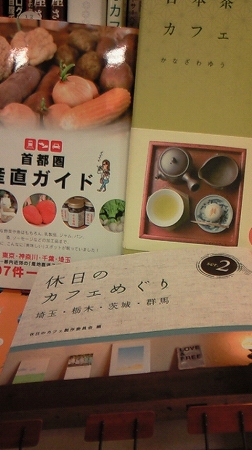男女の出会いへ常総で「常コン」 ~産経新聞20110910~
常総市商工会青年部は10月8日、大規模合コン「常(つね)コン」を開催する。市内の飲食店をバスで移動する「あいのり合コン」として、独身男女に新たな出会いを探してもらうとともに市内の飲食店の活性化も目指す。
参加資格は市内外の20~40歳の独身男女で、男女各100人。2~4人のグループで申し込む。参加費は男性5500円、女性3500円。旧水海道地区4店、旧石下地区4店の居酒屋、すし店、そば店などが会場で、1軒目はグループごとに指定された店を訪れ、その後は自由に店を移動する。開催時間は午後7~10時。
移動は全店を45分で結ぶバスを利用。同部の担当者は「常総市は南北に長く、店と店の間が離れている場合もあり、バスの車内でも出会いのチャンスがある」と話している。
定員になり次第締め切り。申し込みはホームページ(http://www.joso.or.jp/tsunecon/)から専用フォームを利用する。問い合わせは(電)0297・22・2121。
「まちコン」を知っていますか?との問いに
^ ^*答えられませんでした
で、いつものように検索 こういうことへの素早さは人一倍(笑)
ヨコハマ経済新聞に、このようなコメントがありました
ビルの一室で机を並べて「まちづくり」を語る。
それはそれで意義のあることだと思う。
ただそれよりも、街でおいしいお酒を飲んで、純粋に食事を楽しみながら
「まちづくり」を語った方がもっと意義があるのではないか。
一石二鳥である。「まちづくり」と「出会いの場」を創出する「まちコン」が今後、
地域活性にどれだけ役立つのか。温かく見守りたい。
2004年宇都宮の「宮コン」からはじまったのか?
それ以前なのか?
「宮コン」は、宇都宮の街全体で行われている、婚活のためのパーティーです
街全体の飲食店38店舗飲み食べ放題
前回のパーティー参加は、男女合わせて1,500名 男性850人、女性850人
のお店をまわりながら、会話を楽しんだり、食事を楽しんだり・・・
時間は19:00~24:00(23:30オーダーストップ)
料金は男性¥6,500、女性¥3,500です
まちコン人気が飛び火して
蔵の町栃木で「蔵コン」が開催
明日第2回「蔵コン」ナイトです
「蔵コン」での申し込み対象は
■男女各250名、20歳以上の男女・既婚・未婚問わず
■同性2名以上で申込み※お1人様の参加はできません
婚カツとは違った新しい出会いがありそうですよね
1軒のお店に1時間以上の滞在は出来ないと言うルールがあるようです
同じく、明日第1回「諏訪コン」ナイトです
諏訪コンコンセプトは
→たくさんの人とコミュニケーションを取り、たくさんの人と出逢うこと!!
→お店ごとのスペシャルメニューやお酒を、こころゆくまで楽しむこと!!
では、茨城県では?
常総市「常コン」(つねこん)
常総市商工会青年部が主催するバスで移動しながらスマートに楽しむ「あいのり合コン」ですって
この「まちコン」 企画も楽しめそうですね
まちコン総合サイト
休日のカフェめぐりvol2 チェック中
「日本茶カフェ」「産直ガイド」
書店に並んでいる本から、移り変わるニーズを感じます