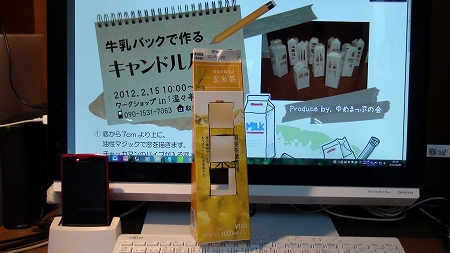取手市議会:監査委選任の同意案再議へ ~毎日新聞20120217~
16日開かれた取手市臨時議会で、市監査委員の選任に関する同意案の採決の際、選任された議員が除斥されずに採決に加わっていたことが分かった。同市議会は3月2日開催予定の定例市議会で同意案を再議することになった。
選任されたのは入江洋一議員(53)。市議会事務局によると、地方自治法第117条の規定により、入江議員は除斥(除外)して同意案を採決しなければならないが、退席しないまま採決したという。議決は有効だが、法令に違反すると認められるため、市長は同意案を再議に付さなければならないという
取手市名誉市民:木内さん認定 「陰から野球支えたい」 ~毎日新聞20120217~
取手市は16日、県立取手二高校野球部と常総学院高校野球部の監督として、甲子園で3回の優勝を果たした同市本郷の木内幸男さん(80)を名誉市民に認定した。名誉市民は3人目。同日の臨時議会で承認された。
木内さんは1957年、取手二の監督に就任。84年の全国大会で優勝するなど甲子園での戦績は8勝5敗。85年に常総学院高校に移り、01年と03年に優勝。甲子園での戦績は32勝14敗。昨年、惜しまれつつ監督を退任した。
木内さんは記者会見で「取手二高で優勝した時、取手の名が全国的に有名になり、野球の力は大きいと驚いた」などと当時を回想。今後について「現場の戦力にはならないので、陰から野球を支えたい」と語った。
取手市:全自主防災組織に災害時優先携帯電話を配備 ~毎日新聞20120217~
取手市は16日、災害時に優先的に使用できる「災害時優先携帯電話」を市内83地区の自主防災組織全てに配備すると発表した。まず40台、その後順次配布し、1地区1台体制を整備する方針。市は全国で初の取り組みとしている。
市は災害時の連絡用と災害復旧活動を迅速に行うため、これまでに小中学校や消防署、JR、担当職員らに優先携帯を108台配布しており、この体制をより充実させる方針。
取手市予算案 2年連続減額 ~産経新聞20120217~
取手市は16日、325億7千万円の平成24年度一般会計当初予算案を発表した。市長選を控えて骨格予算だった前年度当初より1・6%減で、本格予算となった6月補正後と比べても2・5%減となり、2年連続の減額予算となった。特別会計を合わせた予算案総額は543億1700万円。
主な新規事業は、こども発達センター整備事業費1億1千万円▽小中学校耐震補強工事実施設計費2千万円▽高規格救急自動車購入費3500万円▽災害時優先携帯電話配置費125万円▽ウエルネスプラザ(仮称)整備事業費1億円▽LED防犯灯リース料2千万円-など。
10市町村で微量ストロンチウム 県、福島原発との関連否定 ~茨城新聞20120217~
プルトニウムも検出「核実験の影響か」
県は16日、昨年8〜10月に16市町村で採取した土壌の放射性物質検査の結果、県内でも微量の放射性ストロンチウムとプルトニウムを検出したが、いずれも文部科学省が実施した過去の測定結果の範囲内で、福島第1原発事故との関連は認められなかった、と発表した。県原子力安全対策課は、半減期が約50日と短く、事故との関連の裏付けとなるストロンチウム89が全地点で不検出だったことなどから「過去の核実験などの影響ではないか」と推測。「健康に影響はない」としている。
同調査は、県が放射性セシウムなどの濃度測定のため土壌を採取した38市町村のうち、地域バランスや放射線モニタリングの傾向から16市町村を選定して実施。県環境放射線監視センターで同じ土壌サンプルを用いて放射性ストロンチウムとプルトニウムの核種分析を行った。同原発80キロ圏にかかる北茨城、高萩、常陸太田の3市は文科省が調査した。
測定の結果、ストロンチウム90(半減期約29年)は10市町村で1平方メートル当たり290〜54ベクレルを検出。プルトニウムの239(同約2万4000年)と240(同約6600年)は11市町で計同15〜1・3ベクレルを検出。ストロンチウム89とプルトニウム238(同約88年)は全地点で検出下限値以下だった。
文科省が1999〜2008年度に全都道府県で実施した環境放射能水準調査では、各地で核実験の影響とみられる微量の放射性ストロンチウムとプルトニウムが検出されている。本県での測定結果はストロンチウム90が同950〜72ベクレル、プルトニウム238が同2・1ベクレル〜検出下限値以下、プルトニウム239、240の合計濃度が同90〜20ベクレルだった。
今回の結果はいずれも過去の測定結果の範囲内だったため、同課は「原発事故に伴うストロンチウム、プルトニウムの沈着は確認できなかった」とした。
ストロンチウムやプルトニウムは体内に入ると深刻な健康への影響が懸念される。ヨウ素やセシウムと比べて重いため、遠くまで飛散しないと見られていたが、県内でも飛来を心配し、測定を求める声が高まっていた。
取手市議会:監査委選任の同意案再議へ ~毎日新聞20120217~
16日開かれた取手市臨時議会で、市監査委員の選任に関する同意案の採決の際、選任された議員が除斥されずに採決に加わっていたことが分かった。同市議会は3月2日開催予定の定例市議会で同意案を再議することになった。
選任されたのは入江洋一議員(53)。市議会事務局によると、地方自治法第117条の規定により、入江議員は除斥(除外)して同意案を採決しなければならないが、退席しないまま採決したという。議決は有効だが、法令に違反すると認められるため、市長は同意案を再議に付さなければならないという
取手市名誉市民:木内さん認定 「陰から野球支えたい」 ~毎日新聞20120217~
取手市は16日、県立取手二高校野球部と常総学院高校野球部の監督として、甲子園で3回の優勝を果たした同市本郷の木内幸男さん(80)を名誉市民に認定した。名誉市民は3人目。同日の臨時議会で承認された。
木内さんは1957年、取手二の監督に就任。84年の全国大会で優勝するなど甲子園での戦績は8勝5敗。85年に常総学院高校に移り、01年と03年に優勝。甲子園での戦績は32勝14敗。昨年、惜しまれつつ監督を退任した。
木内さんは記者会見で「取手二高で優勝した時、取手の名が全国的に有名になり、野球の力は大きいと驚いた」などと当時を回想。今後について「現場の戦力にはならないので、陰から野球を支えたい」と語った。
取手市:全自主防災組織に災害時優先携帯電話を配備 ~毎日新聞20120217~
取手市は16日、災害時に優先的に使用できる「災害時優先携帯電話」を市内83地区の自主防災組織全てに配備すると発表した。まず40台、その後順次配布し、1地区1台体制を整備する方針。市は全国で初の取り組みとしている。
市は災害時の連絡用と災害復旧活動を迅速に行うため、これまでに小中学校や消防署、JR、担当職員らに優先携帯を108台配布しており、この体制をより充実させる方針。
取手市予算案 2年連続減額 ~産経新聞20120217~
取手市は16日、325億7千万円の平成24年度一般会計当初予算案を発表した。市長選を控えて骨格予算だった前年度当初より1・6%減で、本格予算となった6月補正後と比べても2・5%減となり、2年連続の減額予算となった。特別会計を合わせた予算案総額は543億1700万円。
主な新規事業は、こども発達センター整備事業費1億1千万円▽小中学校耐震補強工事実施設計費2千万円▽高規格救急自動車購入費3500万円▽災害時優先携帯電話配置費125万円▽ウエルネスプラザ(仮称)整備事業費1億円▽LED防犯灯リース料2千万円-など。
10市町村で微量ストロンチウム 県、福島原発との関連否定 ~茨城新聞20120217~
プルトニウムも検出「核実験の影響か」
県は16日、昨年8〜10月に16市町村で採取した土壌の放射性物質検査の結果、県内でも微量の放射性ストロンチウムとプルトニウムを検出したが、いずれも文部科学省が実施した過去の測定結果の範囲内で、福島第1原発事故との関連は認められなかった、と発表した。県原子力安全対策課は、半減期が約50日と短く、事故との関連の裏付けとなるストロンチウム89が全地点で不検出だったことなどから「過去の核実験などの影響ではないか」と推測。「健康に影響はない」としている。
同調査は、県が放射性セシウムなどの濃度測定のため土壌を採取した38市町村のうち、地域バランスや放射線モニタリングの傾向から16市町村を選定して実施。県環境放射線監視センターで同じ土壌サンプルを用いて放射性ストロンチウムとプルトニウムの核種分析を行った。同原発80キロ圏にかかる北茨城、高萩、常陸太田の3市は文科省が調査した。
測定の結果、ストロンチウム90(半減期約29年)は10市町村で1平方メートル当たり290〜54ベクレルを検出。プルトニウムの239(同約2万4000年)と240(同約6600年)は11市町で計同15〜1・3ベクレルを検出。ストロンチウム89とプルトニウム238(同約88年)は全地点で検出下限値以下だった。
文科省が1999〜2008年度に全都道府県で実施した環境放射能水準調査では、各地で核実験の影響とみられる微量の放射性ストロンチウムとプルトニウムが検出されている。本県での測定結果はストロンチウム90が同950〜72ベクレル、プルトニウム238が同2・1ベクレル〜検出下限値以下、プルトニウム239、240の合計濃度が同90〜20ベクレルだった。
今回の結果はいずれも過去の測定結果の範囲内だったため、同課は「原発事故に伴うストロンチウム、プルトニウムの沈着は確認できなかった」とした。
ストロンチウムやプルトニウムは体内に入ると深刻な健康への影響が懸念される。ヨウ素やセシウムと比べて重いため、遠くまで飛散しないと見られていたが、県内でも飛来を心配し、測定を求める声が高まっていた。